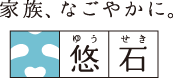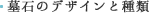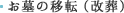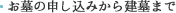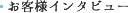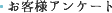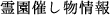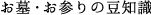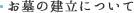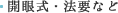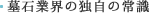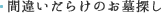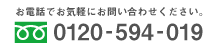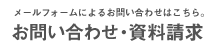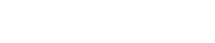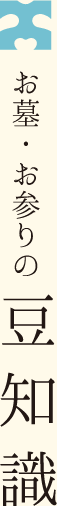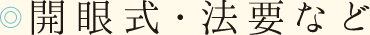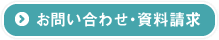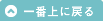霊園内、墓前で法要を行う場合、準備する内容は?
下記の通りです。
- 日時の計画
- 出席いただく方のリストアップ
- お寺様(神職、牧師、神父様)のご都合
- 墓前にお供えする物品
- 法要後の会食の有無と返礼品の準備
- 事前案内の連絡、通知手段。事前案内は一ヶ月前までが適当です。
- ご納骨がある場合は火葬許可証、改葬許可証など
- 上記にかかる予算の確認
お墓を建立した時に行う開眼法要とはどういうことですか。
お墓を新たに建立した時にその石碑に仏様の魂を迎え入れる儀式として開眼法要が行われ、入魂式ともいわれます。
これはお寺がご本尊を新たに迎え入れた時、ご家庭のお仏壇や祭壇を設置したときに行う儀式と同じ意義になります。 なお、浄土真宗では阿弥陀如来様とお墓でご縁をいただくとして、建碑式というかたちで僧侶読経が執り行われます。
お墓を建立する前に地鎮祭を行ってもよいのでしょうか。
本来は、是非行っていただきたいものです。
家の地鎮祭と同じように、土地の神様に「これからこの土地を我が家の聖地として使わせていただきます」という挨拶と「工事の無事完成」を祈願する趣旨で行うものです。
仏式、神式どちらでも地鎮祭は施行できます。お供え物は「海の物」「山の物」「里の物」を用意いたしましょう。
お墓での回忌法要はいつまで行うのでしょうか。
一周忌はお墓の建立と重なる場合が多いようですが、やはり三回忌、七回忌、十三回忌と節目に行っていくのが良いでしょう。七回忌以降はお身内だけで行うことが多いようです。
因みに三十三回忌、五十回忌を弔い上げとして以降は特別に読経供養することはありませんが、祥月命日には、時間の許す限りお墓参りをしたいものです。
仏教徒以外の法要ごとはどのようにすればよいでしょうか。
神式、キリスト系では回忌の期が仏式と多少異なります。
神式は式年祭といい、一年、三年、五年祭と続き十年、二十年、三十年、五十年祭、百年祭となります。
キリスト教は召天日(祥月命日)ごとに記念会、追悼ミサを行い、故人を偲びます。
※それぞれの宗教でも地域の習慣によって多少の違いがあります。
回忌法要が同じ年に重なった場合は、やはり別々に行うものですか。
別々に行うことは理想ですが、参列者の都合や費用も大変です。この場合、回忌が短い祥月命日に合わせ同時に法事を行います。(これを併修といいます) 例=七回忌と十三回忌が重なった場合、七回忌の祥月命日に合わせて行う。
併修しても十三回忌の祥月命日には懇ろに供養しましょう。
※三回忌までは併修はいたしません。
法要後に食事などの接待は行うべきでしょうか。
会食は故人を偲ぶひとときの時間でもあり、久しぶりに親類、縁者が集まる機会でもあります。お墓を建立した時、ご納骨の時は事情が許す限り場を設けたらいかがでしょうか。
なお、この際読経供養していただいたお寺様にも一声かけ、忙しいようでしたら「御膳料」として「お経料」とともにお礼の上でお渡しするのがよいでしょう。